| �@�g�c���A�@���V���L�i�g�c���A�S�W10����R��������ψ���S14/1�j |
���V���L�͏��A���Éi3�N�i1850�N�j21�̂Ƃ��ɏ��߂Ĕ�O���˂ɗV�w�����Ƃ��̗��s���L�ł��B���̒��ɂ����i�́j���ɂ��Ă̋L�ڂ�����܂��B
|
| �@8��29�� |
�w�L�}�̋��Ɏ���A���E�Ɉ�Β�����A�����蓌�A�L�O�����q�̗̂R�����B�����ɑ�Β�����A�����萼�A�}�O���̗R�����B�s�����ƈꗢ�]�ɂ��č���ɏh���B�x
|
�@���A�͗��H����X��������Ă��܂��B�}�O���́u��Β��v�ł��̂��O���̍������ł��傤�B�L�O���q�̂̐͂ǂ̐̂��Ƃ��킩��܂���B����������������܂��A�������Ă��Ȃ��̂�������܂���B
|
| �@9��1�� |
�w���c�h���߂��čs�����Ə����A���䂠��A�O����<�݂��ɂ���>�Ɖ]�ЁA�j�}���O�Ƒ�������̒n�Ɖ]�ӁB������c�㥉Z���얘�A�}���ꖜ�A�ΏB�̂Ȃ�B�x�@
�@
|
| �@9��3�� |
�w���w���߂��ēc���₠��A��̔��r�ɖ傠��A����ɉq������B����߂��ď����s���j�Δ肠��B��ҁA���k���×̗̂R�����B���ҁA���̐��呺�̗̂R�����B�x
|
| �@9��4�� |
�w��������z��B���̍�삵���i���т��������j�K���i�|�ꏼ�j����B����粁i�Ӂj�`�i���j�Δ_�Ȃ�B�R�̒��܂ō����Ĕ��Ƃ��B��̒��ɑ呺�́A���×̂̊E����B�x
�w�i�O���j�É�Ɖ]�ӏ��A���ҋ،\����������Ȃ�B�����̊E�A�F�ؒ�����B�发���ĞH���A�u�����胀�i���ꂪ���j���p�����ؒ�l�Y��㊯���v�ƁB���ɓ�������×̂Ȃ�B�x
|
�@���A�͑呺���A�u�T�R��v���z���u������v�ő呺�̂ƍ��×̂́u�E�v�����A�u�i���w�v�i�Б��j�Ɏ����Ă��܂��B�呺�̥���×̂̋��ł��̂ŁA���×̋����j�Ĉ�i��育���j����䋫�����w���Ă���̂ł��傤�B�u����v�����̌�ʂ����u�����v�ƍ��������̂����m��܂���B�i���H<9��12��>�ɂ��u�����A�T�R�̏���v�Ə����Ă��܂��B��̖��́u������v�������̂ł��傤���H�j
�@�������A���̂Ƃ���ł͐Β�����肪����Ɩ��L���Ă���̂ɁA�����Ɋւ��Ă͋��i�E�j������Ƃ��������Ă��܂���B���A�͔j�Ĉ�i��育���j����䋫�����Ȃ������̂ł��傤���H
�@�܂��A�����i���́j���ɂ͌�����\���ؒ��������Ă������Ƃ�������Ă��܂��B
|
| �@9��12�� |
�w�R���z���č����₠��B�փm���Ɖ]�ӁB���ɑ呺�́A���˗̂̋��肠��B�x
�@
|
�@�ƁA�w�̕����̗̋����Ɋւ���L�q������܂��B���˗̋������������Ă��܂��A�呺�̋������������Ƃ��킩��܂��B |
| �@12��14�� |
�w��㥒}��̗̊E�Ɏ����ꡗ䔒�ʂ̔@���B������C��ځi�Ƃ݁j�ɈقȂ�B�̊E�Ƀj������B��͖ؒ��Ȃ�A�����ĞH���A�u�����萼��͍א�z����̕��v�ƁB��͐Β��Ȃ�A�����ĞH���A�u�����蓌�k�͒}�㚠���ԍ��ߛ��ė̕��x�ƁB
�@
|
�@���J����̋��E���Ɋւ���L�q������܂����A��������̖̐����ł��B�Éi3�N�i1850�N�j�ɂȂ��Ă��܂����̐������Ƃ������Ƃ́A�V�����͂������������ꂽ�̂ł��傤�H �@�܂��A���א�Ƃ͉Éi3�N�i1850�N�j�ɂȂ��Ă��ؒ��ł��������Ƃ��킩��܂��B |
| �@12��26���i�V�w�̋A��͒��肩���������L�O��F���X����k�サ�Ĕ��ɋA��܂��j |
�w����w���߂��A���F�i���G�j�Ɖ]�ӏ��Ɏ���ߎ`��`�ӁB�s�����Ə����A�}�㥒}�O�̋��A��Β������B�R�ƂɎ�����s���B�x
�@
|
�@�ƁA�n�s�E���G�̍������Ɋւ���L�q������܂��B |
| �@��쑊�����C�@����O�Y���i���a11�N11��5�����s�j |
�@���Ɩ���̕������a11�N�ɏ����ꂽ�u��쑊�ߕ��C�v�Ƃ����{������܂��B���̖{��ǂ߂Α��߂��ǂ̂悤�Ȑl�ł������������ڂ낰�Ȃ���킩��܂��B
�@���̒��ɍ����Ɋւ���L�q�iP302�j������܂��̂ň��p���܂��i�����͉��߂Ă��܂��j�B���A�����Ɋւ��Ă͒��쌠�@��̒��쌠�ی���Ԃ͌o�߂������̂Ɣ��f���Ă��܂��B
|
| �@�w�}�O���X���́A�e�ˋ��E�̗v���Ɍ��Ă��Ă��܂����A�����̑����͑��߈ȗ��e��ɘj����|�����߂�ꂽ���̂ŁA�w�]���k�i���j�i���쒆�����k�j�}�O���x�t�B�����āA�u�k���O���A���y�������k���e�ꖇ�B�E������Ď��i���j���ڕ���ژZ�������ܐ��V���v�Ƃ̋L�ڂ��c���Ă��܂����A�ʂ��Ď����̒N�̏��ʼn����Ɍ��Ă����̂��A����<�͂��܂�>�������ċ�����̂��A����<���̂�����>�����v�����˂܂��B�}�㋫�̂��̂͑��߂̏��ɑR���ׂ��A�}��ɉ��Đl����<����>�ߊm���������ʂ��M�҂ɑI��A�����Ɍ������ꂽ���̂�����Ƃ������ƂŔV�͌������Ă��锤�ł��B�x
�@���u�Ď��v�Ƃ���܂����A����͌��ݎ��B�������Ď��i��ЎD���Ɏg���镶���̌`�ԁj�ł͂Ȃ��A�傫�ȕ������������ɗ֊s���ɏ������̒���h�肱�Z�@�̂��Ƃł��傤�B
|
�@�����ǂނƍ����̖��Ɋւ��āA���Ƃɂ͑��߈ȍ~�̊e�㍇�킹�Ă�5��̋L�^�����Ȃ����Ƃ��킩��܂��B
�@5��̂����A
�@�u�]�����}�O���v���O���i�k��B�j�̍����ł��B�i�V��5<1834>�N�����j�i�}�O���䋫�ړ��L�ɑ��߂��˗����ꂽ�L�^����j
�@�u�]���k�}�O���v��3��́A
�@�܂��}�㋫�̐͌����̌o�܂����n�s�i�}����s/����}��͉��G�j�ŊԈႢ����܂���B
�@���Ɂu�k�v�Y������̂����c�i�}����s�j�̐ł��B���̐Ɋւ��Ă͖��m�ȋL�^���c���Ă��Ȃ��̂ł����A�O���̐���Ɍ��Ă�ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�O���̖���V��5�i1934�j�N��7���ɏ����Ă��܂��̂Łi������9���j�A���̌�ɑ��߂����������̂��Ƃ���ƁA���ߍŔӔN�̂��̂ɂȂ�܂��B
�@���߂͓V��7�i1836�N�j9��27���Ɏ������Ă��܂��B����ɁA���̑O�N�V��6�N7���ɑ��߂̒��N�̌��тɑ���2�̉����������Ă��܂����A���̎��A���߂͂��łɕa�ɉ点���Ă��莩��q�����邱�Ƃ��o���܂���ł����B���̂��Ƃ��l�����킹��ƌ��c�͎̐O���Ƃقړ������i1�N����킸�j�ɏ����ꂽ���̂ł��傤�B
�@����3��i��3��j�͕��ׂĂ݂�Ƃ킩��܂����{���ɂ�������ȕM�Ղł��B
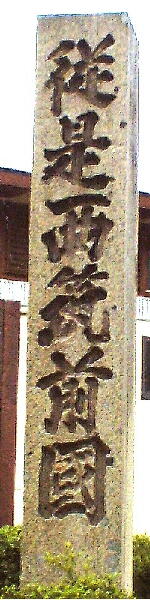 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�u�k�v�Ə����ꂽ����1��ɊY��������O�����i�����s�j��������܂���i�A���O�����̖��́u�n���k�}�O���v�j�B���͉̐������當��15�i1818�j�N�����ł��邱�Ƃ��m�肵�Ă��܂��B���߂͖��a4�i1767�j�N�`�V��7�i1836�j�N�����l�ł�����A���̐������˂̏��w�t�ł��������߂̏��������̂Ƃ���ׂ��Ȃ̂ł��傤�i���Ɏ������̐ɑ��߃}�[�N��\���Ă��܂��j���A���3��̖��Ƃ͂��Ȃ�C���[�W���Ⴂ�܂��B���͂���𑊋߂ƌ����邱�Ƃ��o���܂���B
�@���������̐̃T�C�Y�͕�45cm�����240cm�i���݂̘I�敔�j�ł�����A�u����ژZ�������ܐ��v�i��48.48cm�����318.18cm�j���炷��Ǝ�������ƌ��킴�链�܂���B
�@���������̐��u�k�v��3���̂�����1���ɂ��Ă��܂�Ȃ��ƁA�k�Ə����ꂽ�u����ژZ�������ܐ��v�̑傫�Ȓ}�O�������A������L�^�ɑS���c�炸�ɂЂ�����ƌ����Ă��āA�������Ȃ��Ȃ����ƌ������ƂɂȂ�܂��B
 �@�O���� �@�O�����@�Ō�Ɏc�����u�]���쒆�����k�}�O���v�́A���̓��ꐫ�������Y�̗̋��ŊԈႢ����܂���B
�@���͍]�ˎ��㒆���ȍ~���ے������ɂ́u���v�̕����͎g���Ȃ������Ƃ��������̂��Ă��܂��i���������y�ї̋��ɂ͑�������j����A���̖��͗̋��Ηp�̂��̂ł���ƍl���܂��B
�@�A���A���ۂ̉��Y�̗̋��̖��́u�]���쒆�����k�������v�ł��B��ŕ��ׂĂ��܂����A���Y�̗̋��͑���3��̍����ƈႤ�����������܂��B�܂��A�u�]���v�̕��������������C���ł���B�u���v�̕��������ɔ�ׂ�Ǝ�������o�����X�Ɍ������B
�@������ǂ��������邩�A�������������̗]�n������܂��B
�@�����������N���ɕ��ׂ�ƁA
�@�O�����@�i1818�N�j
�A�n�s�@�H�@��1
�B���Y�@�i�}�O���䋫�ړ��L�Ɂu�O���͉��Y���Q�l�ɂ����v�Ƃ̋L�ڂ���j
�C�O���@�i1834�N�j
�D���c�@�i�����N�s����O���̌�Ƃ����Ă���j
�@�ƂȂ�܂��B
�@��1�@�n�s�͐��m�ȔN��s���ł��B��d�i��b�ρj�̌`��O�𥌴�c���O�ƌ����Ă��܂����A�}�㑤�̖������������c�C���i��2�j��1798�N���܂�ł��B�}�O�̐����đւ�����̂ł����ɒ}�㑤���R�����Ƃ����`����M����A�}�O<�n�s>�ƒ}��<���G>�̐̌����N��10�N�����Ȃ��ƌ������Ƃł��傤�B�O�����������ɍ��c�C����20�ł�����A�n�s�Ɖ��G�̌����̎������l�����Ƃ��Ă��A�n�s���O�������O�ƌ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@��2�@��쑊�ߕ��C�ɂ́u�m���������ʂ��M�ҁv�ƂȂ��Ă��܂����A���n�̏��S�s�͍��c�C���Ƃ��Ă��܂��B
�@���Ƃɂ͂���5����L�^�Ɏc���Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����A�������L�^�R������邩������܂��A�u����ژZ�������ܐ��v�̑傫�Ȗ������������݂̂��L�^�Ɏc�����Ƃ��l�����܂��̂ŁA���̋L�q�݂̂������ē��Ƃ�����������5����Ȃ��ƌ��ߕt����킯�ɂ͂����܂���B
�@�}�O�ɂ͂���ɑ��߂��������ƌ����Ă���������܂��B���̒��ʼnG�����̍��������͑��߁i�������͑��߂̉e�������l�j�炵�������������܂��B
 �@�G���� �@�G�����@���̐̕����͂ǂ�����Ď��ŏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ������ł��̂ŁA�ς��ƌ������C���[�W���Ⴂ�܂��B�������A�ꕶ�����悭�݂�Ɗm���ɑ��߂炵�������������Ă��܂��B�ƁA�����ɑ����̋^��������܂��B�Ⴆ�Ȃ��u�}�v������ȂɉE�ɂ���Ă��܂����̂ł��傤���H�������u�}�v�����ꂽ�͖̂����������l�ł͂Ȃ��H�̐ӔC�͈͂Ȃ̂�������܂���B
�@���̐́A����1����傫���i����ژZ�������ܐ��j��������ɂ��Ă����Ƃ̋L�^�ɂ͂Ȃ��ł��B
�@���A��쑊�ߕ��C�ɂ͑��߂��������Ƃ���鏑�̎ʐ^�����t�ڂ��Ă���A��������������ꂼ��̑��߂̕����̕��͋C�����邱�Ƃ��ł��܂��B
|
|
|

